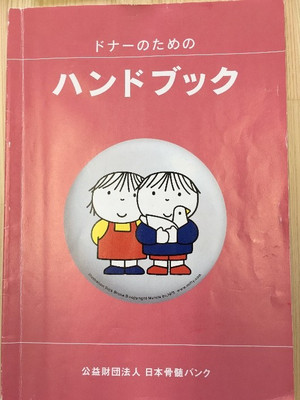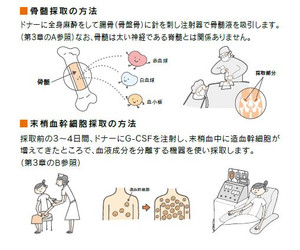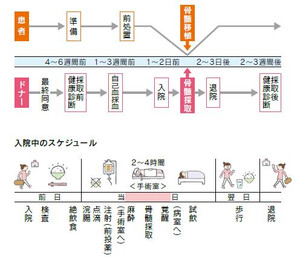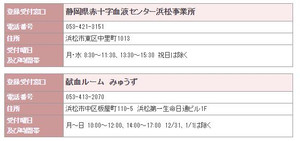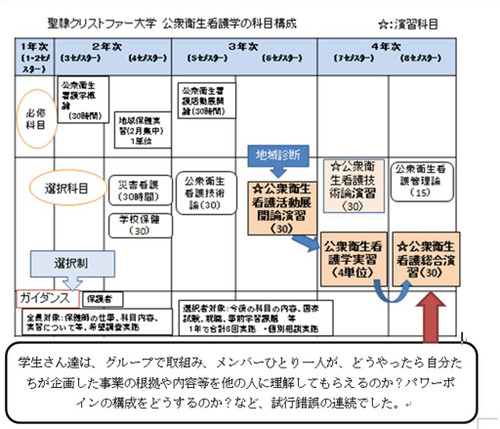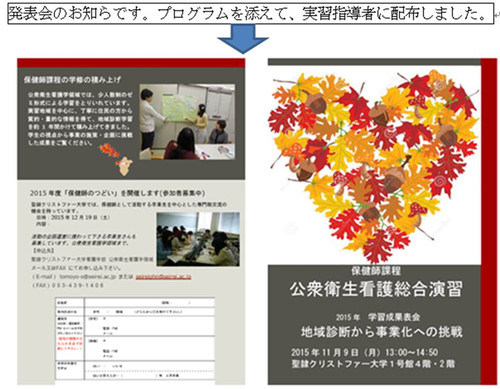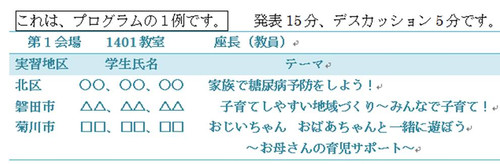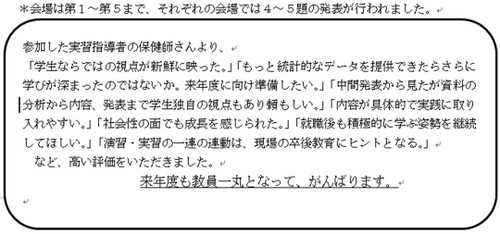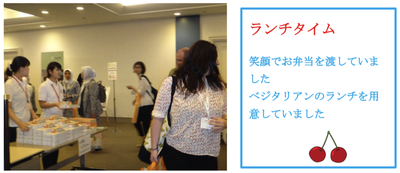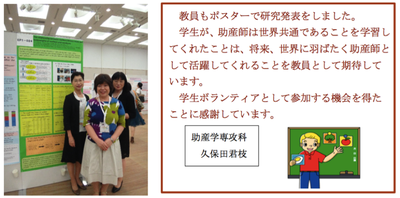Happy New Year!
I wish you all the best in 2016!
皆さま、本年もどうぞよろしくお願いします。
さてさて、新しい年が始まりました。
新年、といえば「抱負」ですね!
ちなみに英語では、New Years' Resolutions といいます。
新しい年を迎えると気分もウキウキ、今年こそ色んな事にチャレンジしよう!とう気持ちになりませんか?
今年こそ、と毎年意気込んでは何かと三日坊主になりがちなあなた(私もです…)、まずは目標を立てる事から始めてみましょう。
目標を立てるだけでも、何も立てない人より達成できる確率が上がるのだとか。
今年はこれを頑張るぞ!と周りにもどんどんアピールするとよいですね。
さてさて、日頃授業や実習で忙しい日々を過ごしている看護学生さん達ですが、この3月には2年次生10名がアメリカ看護研修への参加を予定しております。
彼らにとって、この研修はワクワク、ドキドキ、大きなチャレンジである事は間違いありません。
本学は、アットホームで専門分野も学べる国際交流が盛んな大学で、複数の高等教育機関と交流協定を結んでおります。
3月の研修先は、カリフォルニア州オークランド市にあるサミュエルメリット大学。
昨年度から研修生の受け入れ・派遣がスタートしております。
出発までにはもちろん事前研修がありまして、全部で6回行われます。
皆さんが現地で安心して研修に専念できるように、安全面でのオリエンテーションはもちろん、病院や施設見学、学内演習、そしてホームスティ先で、より豊かな経験と学びが得られるように、様々なプログラムを用意し、我々国際交流担当の教職員が全員体制でバックアップしております。
昨年12月21日(月)には第2回事前研修が実施され、英語学習に関するオリエンテーションと実践練習を行いました。
冒頭で英語学習のコツや教材について解説をした後は、いよいよ実践編です。
① 自己紹介
② とっさに答える練習(レストランでの会話)
③ 英語でのデモンストレーション(紙飛行機の折り方)
自己紹介はそれぞれ準備をして臨んでいるのですが、今年のメンバーは、何と言ってもその積極性が素晴らしい!各自用意してきたはずのセリフが書かれた紙は見ず、相手の目をしっかり見ながら会話を試みています。上手に質問を挟みながら、頑張って英語で話し続けています。

横では、引率の先生も一緒に参加してくれていました。こういう一体感がいいですね。
担当より、ちょっとしたアドバイス。
リアクションを大きくね。日本人の話し方、ジェスチャーは、英語でのコミュニケーションではちょっとおとなしすぎます。役者になった気分で、ちょっとハイに、大げさに言うぐらいがちょうどよいですよ!
2回目は立ったまま自己紹介、パーティーをイメージして練習。そうそう、みんな、いい感じ。

次は、とっさに話す練習。
私達日本人は、頭の中には習った英語が沢山詰まっているはずなのに、使う機会が少なすぎて、いざ使おうと思うと出てこない。ベテランペーパードライバーの方が多いですね。
研修中はレストランで食事をする事も多いので、店員さんとのちょっとした会話を練習しました。
場面は食事が終わってデサートを注文するところ。
CDですが、ウェイターのお兄さんがいきなり話しかけてきます。
Waiter: How was your meal?
Students: ‥‥
デザートのオーダーを聞かれ、サイドにアイスクリームを載せるか聞かれ‥みんなの口がモゴモゴしている内に、1回目は終了。
日本と違って、海外のレストランでは店員さんと話す機会が沢山あります。メニューには写真もないので、注文するのにも、色々と質問をする必要がありそうです。
知っているはずの英語が口から出てこない事実を体験した後、返事の仕方を学習。
なんだ、こんな簡単な返事でいいんだ。
そうです。簡単な返事でいいんです。
大切なのは、何か話す事。
日本語には「沈黙は金」ということわざがありますが、一歩外へ出たら「沈黙は禁」ですね。
拙くても構いません。なんとかコミュニケーションを取り続けましょう。その前向きな姿勢がきっと伝わります!
2回目はスムーズにやり取りができましたね。これでレストランでの会話もどんと来い。
現地でいいレストランを見つけたら教えてね♪
最後は英語でのデモンストレーション。
研修中には、現地の学生との交流があり、施設を訪問することもあります。
そこでは、何かと歌や芸?などをご披露する機会があるのですよ!
この日に習ったのは紙飛行機の折り方。

折り紙はなかなか使えるツールです。
ペアの片方にだけ折り方を見せて、後は相手に頑張って伝えます。
2つに折りましょう。
Fold in half.
ひっくり返します。
Turn it over.
簡単簡単。

できたかなー??
さーて皆さん一列にならんで、One, two, three …

Go〜!!
飛んだ飛んだ〜‼

Wonderful!
Amazing!
引率の先生も、大きく感動を伝える大切さを教えてくれました。

なんだか、私、話せるかも!!という自信がついたのではありませんか?
そうです。その自信が大切なのです。
伝えたい、という気持ち、知りたい、仲良くなりたい、楽しみたい、という皆さんの気持ち、どんどん伝えてください。
分からない事だって、コミュニケーションのきっかけ。聞かれる方も楽しいものですよ。
さあ、3月の夢に向かって、飛んでいけ〜!!
みなさんの成長が楽しみです。
看護学部 英語担当 渥美