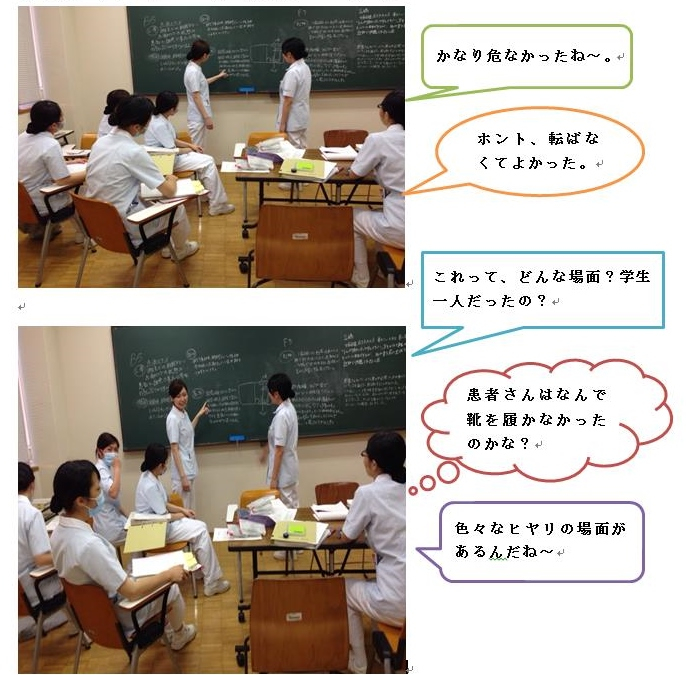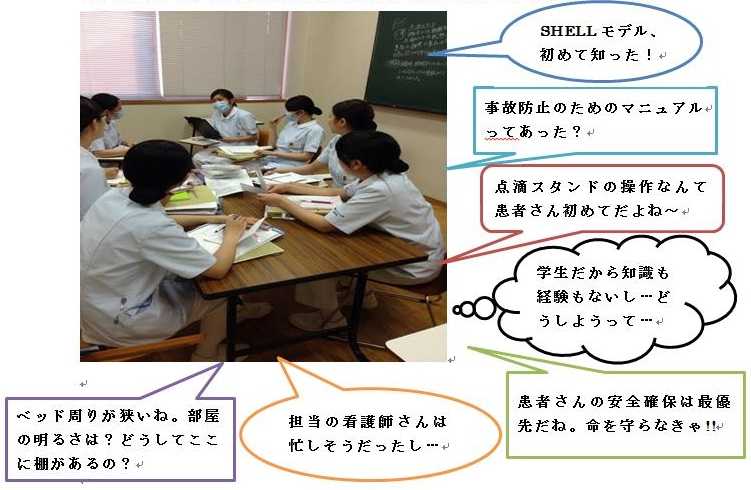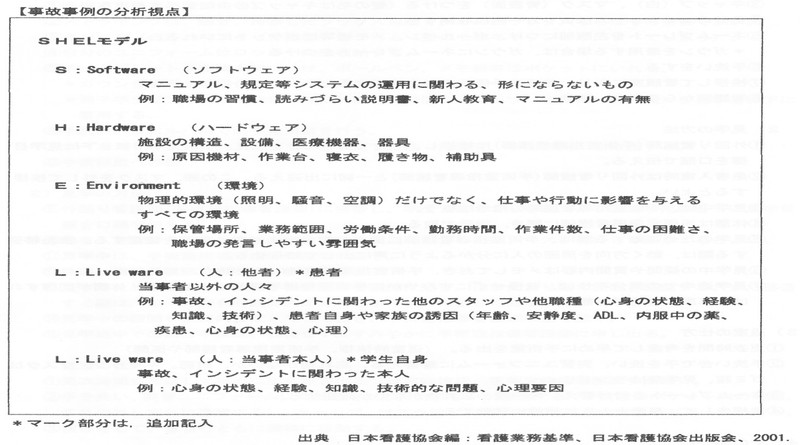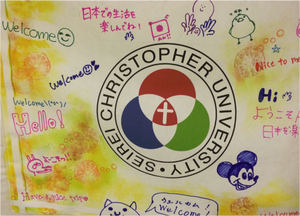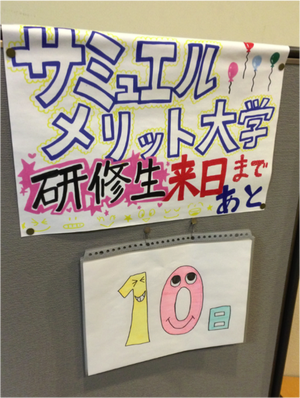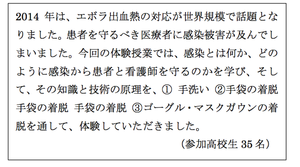在宅看護学実習 終了しました!
2014年10月20日から開始した在宅看護学実習が、2015年6月19日に終了しました。
2週間実習、159名が履修しました。
学生が同行訪問することにご協力いただきました地域の皆様、
実習施設のスタッフの皆様、ありがとうございました。
実習施設の学生駐輪場の栗の木も、冬の姿から、
6月の青々とした姿に変化しました。日々栗の木に励まされ頑張りました。
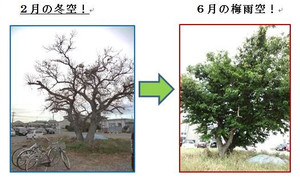 2週間実習、1日間はケアマネージャーさんと同行訪問をさせていただきました。
2週間実習、1日間はケアマネージャーさんと同行訪問をさせていただきました。
今日は、大学に隣接したケアマネージャーさんの事業所実習なので、歩いて移動します。
5日間は、訪問看護ステーションで同行訪問をさせていただきました。
学生が後部座席に乗り込み出発するところです。1時間の訪問看護頑張りましょう!
 スタッフカンファレンスにも参加させていただき、福祉機器取扱いの勉強会も参加してきました。
スタッフカンファレンスにも参加させていただき、福祉機器取扱いの勉強会も参加してきました。
2週間実習最終日は、全員が帰校して、まとめのカンファレンスを行います。
学生の発表を傾聴し、ディスカッションをしています!なんだか楽しそうです。
このグループはカンファレンスが終了して、
学生による実習評価を行っています。
教員も学生から評価を受けます。
教員は席を外して学生が評価しやすい環境を提供しています。
写真の掲載については、実習施設・学生からの許可を得て掲載しています。