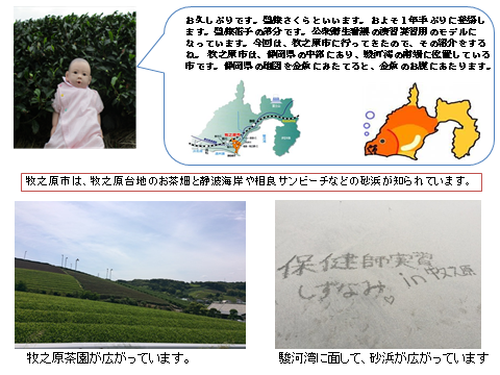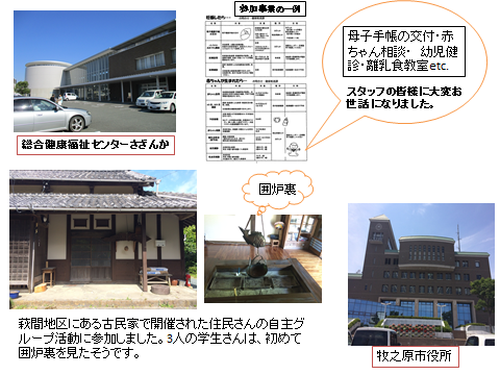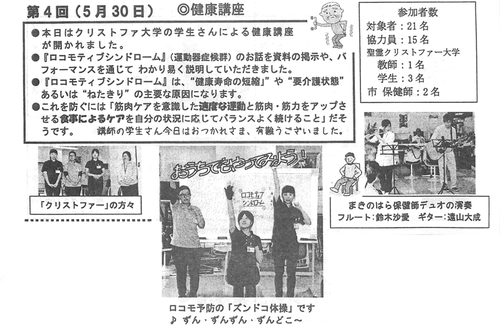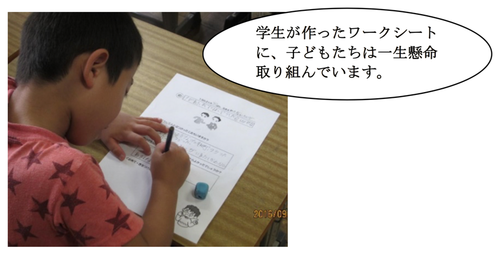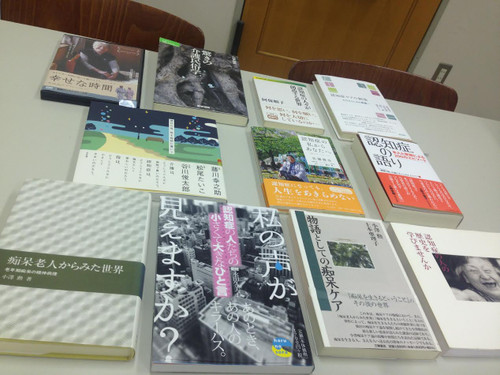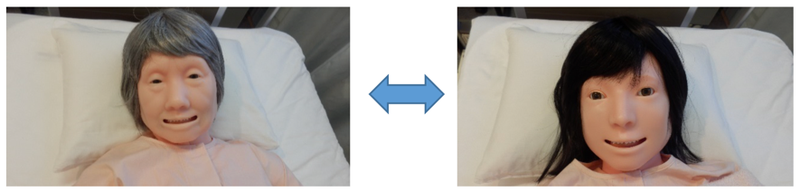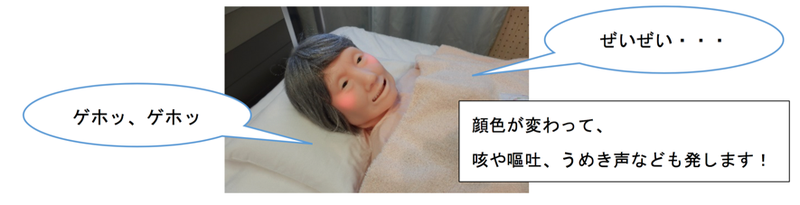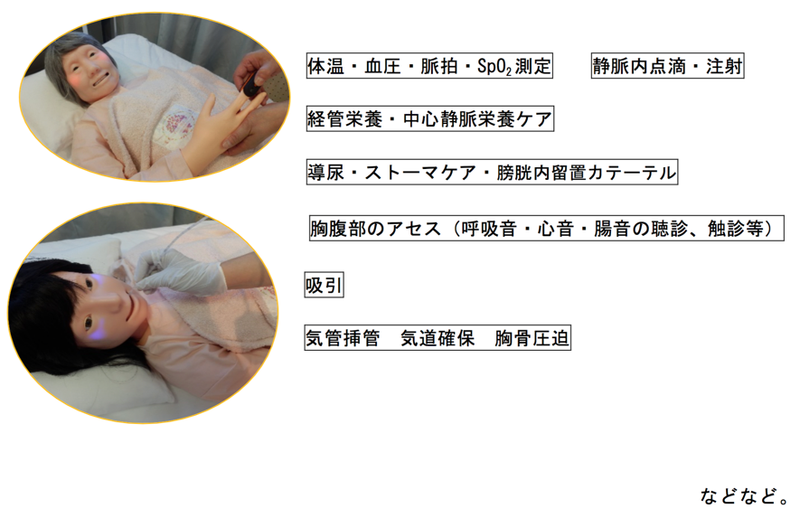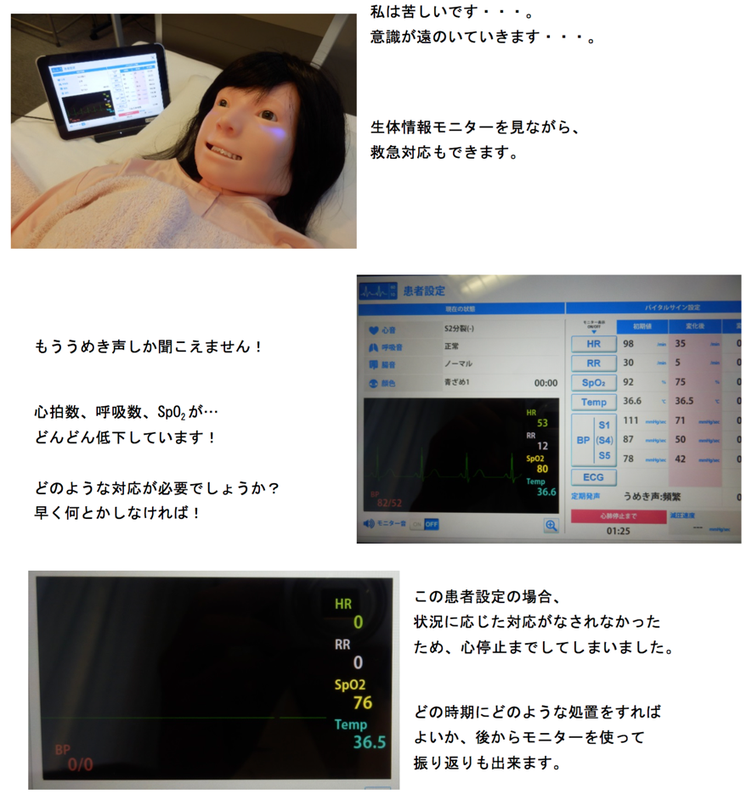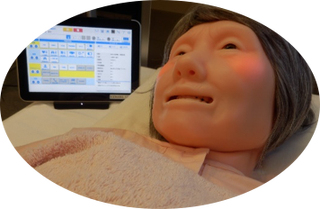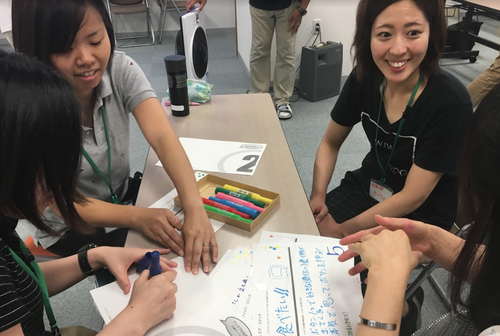学生レポート:聖灯祭
コートやマフラーなど、防寒具をよく見かけるようになりました。学生たちも、寒さに負けず冬の装いで毎日元気に通学しています。
聖灯祭が11月5日行われました!多くの人が訪れ賑わっていたようです。私の友人も出店していて、他学部との交流もでき楽しかったと話していました。参加する側も主催する側も楽しめるよい聖灯祭だったようです。

大学の中庭は、学生はもちろん先生方や近隣の人々の憩いの場になっています。サッカーをしたり、散歩を楽しんだり、置いてあるベンチで談笑していたりする姿をよく見かけます。多くの人が集う中庭の紅葉も見事です。思わず写真に収めたくなる鮮やかさです。上を見上げると秋の明るい青空と、赤や黄色の紅葉が心をリフレッシュしてくれることでしょう。

皆様、暖房と外気温の温度差で体調を崩さないようにお過ごしください。
(ブログ担当:くらりす)