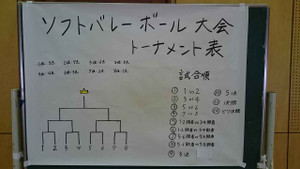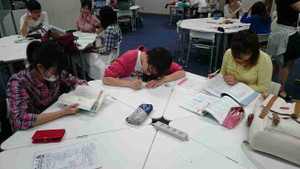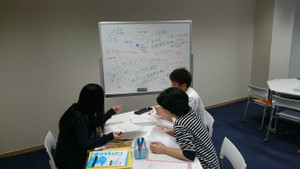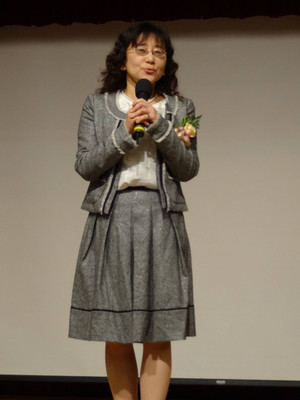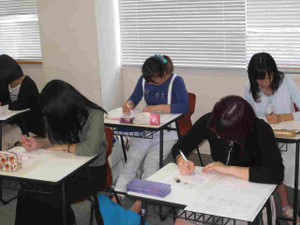学生交流会①
5月30日に学生交流会が開催されました。
1年生、2年生、3年生の親交を深めることを目的に、3年生が主体となり企画をしてくれました。
先輩と後輩のつながりは、学生時代だけではありません。
将来言語聴覚士として働いたときに情報を交換したり、共同研究をしたりと関わる機会が多々あるかと思われます。絆は大事ですね。
皆が集合する前に幹事が準備を進めています。受付の位置を決めます。
受付の場所が決まった後は、参加者の氏名が分かるように、氏名を書くテープの用意です…。
そして他の幹事はソフトバレーの準備を進めていました。
準備万端。いよいよ交流会がはじまります。まずは「開会式」。
大城学科長からご挨拶を頂きました。
怪我をしないように皆でラジオ体操をしました…。
「ラジオ体操なんて何年ぶり?」なんて声が聞こえてきました…。
準備体操が終わって、いよいよゲームの開始。
ウォーミングアップを兼ねて、サイレントゲームから始まりました。
このゲームは、声を出さずにお題に沿って集まったり、並んだりするゲームです。
最初のお題は血液型です。皆ジェスチャーで伝え、何とか集合できました。
ST学科はどの血液型が多いのか、私も非常に興味がありました。
内訳をみてみると‥
A型が半数以上を占めていました。
B型は少ないですね。
A型の次に多いのがO型ですね。
AB型です。
あれっ? A型、B型、O型、AB型でもない方が数名いますね。
日本人の血液型は、A型が4割、O型が3割、B型が2割、AB型が1割と言われていますので、ST学科は若干A型の割合が多そうです…。
次のお題は誕生日です。
ことばは使わずに、ジェスチャーだけで意思の疎通を図っています。
何とか並ぶことができました。
間違っている人も何人かいました。
その間違った人は教員でした。
そして、なんと交流会の日が誕生日だった学生が2名いました!
おめでとうございま~す!!
サイレントゲームの後は、ソフトバレーボールを行いました。
ソフトバレーボールは、8チームのトーナメント制。
得点を決めたら皆で分かち合う、それがチームですね。
学年を超えた友情…。 青春ですな~~~!!
優勝チーム!! おめでとうございます!
バレー経験者がいたのかな???
サイレントゲーム、ソフトバレーが終わり、お昼休憩の時間です。
グループごとにカフェテリアでお昼を食べました…。
ここまでが午前中のプログラムでした…。
午後は次回報告します!お楽しみに!