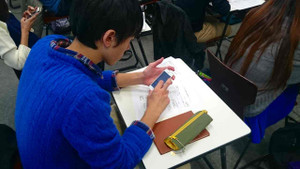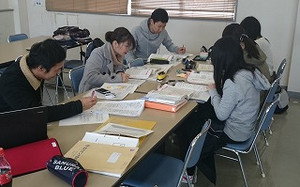本日は聖灯祭当日のことを紹介します。
まずは、3302教室で行われた健康祭の様子です。
健康祭とは、各学部・学科を紹介するイベントです。
今回、言語聴覚学科では1~2年生が中心になり、①聴覚コーナー、②高次脳コーナー、③嚥下コーナー、④小児コーナーを設けて、紹介しました。
聴覚コーナーを覗いてみると…

すごい…、非常にたくさんの方がいらっしゃいました。
少し時間を置いて行ってみると、見覚えのある方がいました。

大城学部長兼学科長です。聴力検査を受けていました。
「最近聞こえにくくなってね…」と聞こえにくさを訴えていました。
学生は緊張していましたが、授業で習ったことを思い出し、きちんと検査をしていました。
そして、検査後、「先生の耳は正常ですよ」と一言。
大城先生もほっと一安心。良かったですね、大城先生。
さて次は、高次脳コーナーです。
言語聴覚士が行う高次脳機能検査を体験していました。
こちらは積木模様といい、構成機能をみる検査です。

「この検査は〇〇をみる検査です」、「結果は〇〇でした」など体験していただいた方に説明をしていました。

検査目的や方法、結果の説明も言語聴覚士の役目ですね。
素晴らしい!

嚥下コーナーでは、嚥下食を試食していました。
摂食嚥下障害者は、口からエネルギーや水分を取ることが難しくなります。
そこで、食事を咀嚼や嚥下しやすいように、やわらかく仕上げます。
これが嚥下食です。エネルギーや水分摂取に関わることですので、とても大切な食事です。

参加された方から「あっ、意外とおいしい」との声が聞かれました。
今度は模擬店を紹介します。
言語聴覚学科の学生は、「ワンタンスープ」を作りました。

準備を頑張って行っていました。

このワンタンですが、皮から一つずつ作ったそうです。
全て手作りだそうです。
私も食べましたが、とても美味しかったです。
来年も提供するそうですので、ぜひお楽しみに!
他の模擬店を見ていると、「先生、買ってください」との声が聞こえました。

こちらのお店ではワッフルを売っていました。
甘い物好きの木原先生は思わず「ニコッ」としながら買っていました。
嬉しそうですね。
健康祭、模擬店だけではありません。

ハンドベルを行っている学生もいました。
さらに、3年生も参加していました。

初めての学園祭を満喫していました。

美味しかった食べ物は、「ワンタンスープ」と「揚げたこやき」だったそうです。
最後になりますが、ST学科で聖灯祭の実行に関わった学生です。
パーカーを皆で揃えたそうです。

実行委員の皆様、本当にお疲れ様でした。