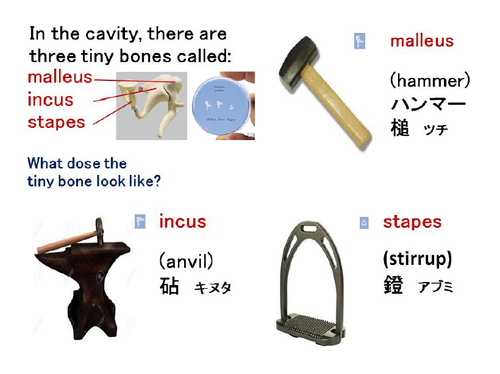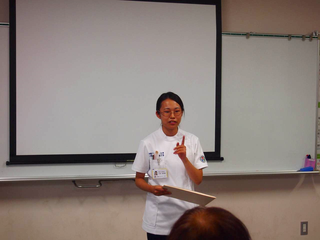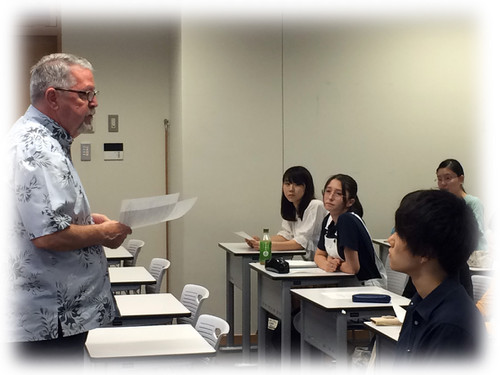今回は、普段の勉強や臨床において重要となる、クリティカル・シンキングについて考えました。マックリーン先生から、クリティカル・シンキングについての説明がありました。
皆さんが見聞きしたことが、本当であるか判断すること、論理的に考えること、議論の内容をそのまま信じず、確認し・議論し・分析することが必要だということ…これまでの皆さんの学び方とは大きくことなる姿勢ですね。ただ、これらの姿勢は、皆さんが深く言語聴覚療法を学び、患者さんを十分に理解し、臨床で臨機応変に適切な対応をしていくためには欠かせないことになります。これまで学んできた、話の構造化にも繋がる大事なポイントです。
クリティカル・シンキング…なかなか難しいことですが、これからの大学生活、勉強、様々な経験のなかで、少しずつこのような考え方を身につけていけるようにしてきたいですね。
************************************
What are the central goals of education, and what are our goals at Seirei Christopher University? It should never be just to pass a national exam alone. In fact, passing a high stakes national exam, while important, is really a distraction for the real goals of education. Education is about growing to be the best person possible, within a specific academic discipline, or at least it should be. Educationally, we seek to develop students with advanced and mature “Critical Thinking Skills.” This means developing students with:
1) Curiosity
2) Skepticism
3) Humility
4) Reasoned Judgement
5) Logical Thinking Abilities
These skills, when applied within any professional context, make any student the best professional among your peers. Socially, Seirei Christopher University seeks to develop students with a deep, authentic, and lifetime commitment to others. We seek graduates who will act as the foundational resource for helping others in need. This is what we mean by Love Thy Neighbor.
MacLean
************************************

今回の勉強会の紹介は、秋本さんと梅木田さんにお願いをしました。
** 秋本さん *********************
ST学科1年、第5回スキルアップ勉強会が行われました。 今回学んだことは「critical thinking」批判的な思考を持つということです。
批判的思考を行うためには3つの事柄が必要であると教えていただきました。
1つ目は「Curiosity」 好奇心 2つ目は「Skepticism」疑い 3つ目は「Humility」 謙虚
です。この事柄は仕事や討論・議論・学習の面において必要なスキルとなることも教えていただきました。
この3つの事柄をふまえて、普段の授業の内容や教科書でも疑問を持つことが大切だと感じ、また、その根拠となる証拠を自分で探すことの必要性も学ぶことができました。
************************************
** 梅木田さん *********************
第5回定期勉強会が、10月26日(木)に開催されました。今回は、マックリーン先生、石津先生のご指導の下、クリティカル・シンキングについて学びました。
クリティカル・シンキングには、Curiosity(好奇心)・Skepticism(懐疑)・Humility(謙虚)が求められます。私は、Skepticismが求められることが、強く印象に残りました。相手の話が正しいのか、どうしてそう感じたのか、根拠はあるのか、などの疑いの目を向けることにより、思考がより強固なものとなる、ということを教わりました。
しかし、Skepticismは、決して簡単なことではない、と感じました。なぜなら、私は、人と話をする際には、その話が正しい、と思い込んでいるからです。特に、自分の知らないことについては、このような傾向が強くなります。
私は、ある物事について主体的に考えない限り、疑いの念を抱くことはできない、と思います。これからは、得た情報を鵜呑みにするのでなく、自ら疑問を持ち、自分が納得できたら、受け入れるように心がけます。
************************************