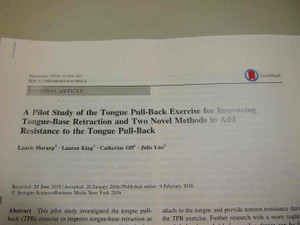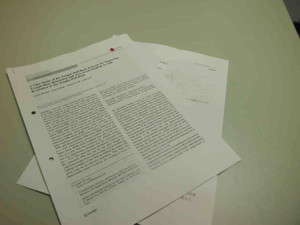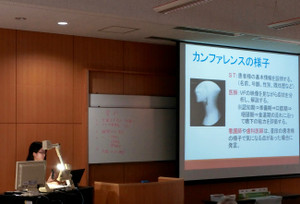浜松言友会にテレビ局が取材に来ました
教員の谷哲夫です。
10月30日(日)の浜松言友会例会(アイミティ浜松)に静岡第一テレビの取材班が訪れました。
10月9日(日)に静岡市で開催した吃音講座がきっかけで、事前に取材の申し入れがあったため、
私は例会開始1時間前に会場に到着して取材を受けました。
カメラを向けられながら吃音に関する様々なことを質問され(質問内容については事前の打ち合わせなし!)、
少し緊張しながら説明しました。取材班のスタッフに、
吃音のことを真剣に理解しようとする姿勢が観られたことには大変うれしく感じました。
例会の様子も撮りましたので、出席した会員は若干緊張気味でしたが、
次第にいつものように和やかな雰囲気で会話ができてきました。
・・・と、ここで事件が起きました。
休憩中に私が外から会場に戻ったら、取材班が出席していた谷ゼミの学生にインタビューを始めていたのです。
私はこれに驚いて、思わずとった行動は、この状況をスマートフォンで撮ることでした。
吃音の啓蒙活動は浜松言友会の活動のひとつであり、また、教員としての私の役目でもあります。
浜松言友会の活動に、メディアに携わる方が関心を持っていただいたことは大きな効果だと考えます。
放送予定についてはまだわかりませんが、わかり次第報告させていただきます。
佐藤さんが真剣に答えています。左の豊田さんと赤堀さんは恥ずかしそうです。
真剣に答える佐藤さん(ちょっと逆光ですみません)。