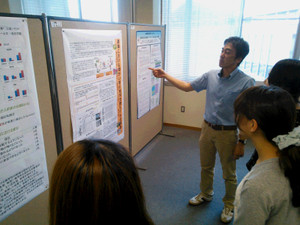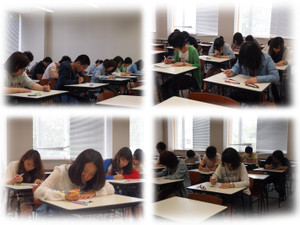2014年6月 6日 (金)
2014年6月 2日 (月)
2014年5月30日 (金)
職場紹介(卒業生)
常葉リハビリテーション病院で言語聴覚士(ST)として勤務している田中悠倫子(1期生)と、中嶋祐里(6期生)です。
当院は、浜松市内にあるリハビリ専門病院です。STは3人いて、毎日10人ほどの患者さんを各々担当しています。対象にしている患者さんは、脳梗塞や事故などで脳に損傷を受け、言葉がうまく話せなかったり、口からうまく食べられなくなったりした方が多いです。
土日を含め毎日リハビリを行っているため、担当者が休みの日には、代理のSTが訓練をしています。そのため、お互いの患者さんについてしっかり情報交換をしています。そこから訓練方法のアドバイスをもらえたり、多くの患者さんとかかわったりすることで知識の幅も広がります。
就職してからも学ぶことがたくさんあり、反省も多いです。ですが、患者さんやご家族が訓練の時間を楽しみにしていてくれたり、「話しやすくなった」「おいしく食べられるようになった」と改善がみられたりすると、これからもがんばろうと感じます。
今後もSTの必要性は高く、更に人数を増やし多くの患者さんに対応できるようにする予定です。
聖隷クリストファー大学は、コミュニケーション障害の講義だけでなく、摂食嚥下(食べること)の講義や演習も豊富にあります。当院だけでなく、今どこの病院でも摂食嚥下障害の改善を希望する患者さんが多くいらっしゃいます。講義で習った観察ポイントや訓練方法が、臨床でそのまま役立っています。
言語聴覚学科の学生は、各学年20人前後と少人数だったため、繋がりもとても強かったです。卒業してからも、他の職場に就職した友達に、訓練方法や患者さんとのかかわり方について意見交換をし合ったりしています。
また、大学の図書館は卒業生も利用することができます。仕事が終わった後に図書館へ行って、リハビリに役立つ本を探せるので、今も活用しています。
病院の玄関です。
言語室です。少し狭いですが、患者さんが充実した訓練時間を過ごせるよう心がけています。
病院の受付にて。診療時間には、多くの外来患者さんがリハビリに来ています。
2014年5月29日 (木)
言語発達障害学Ⅰ(2年生)
前回の授業で「WISC-Ⅲ知能検査」を練習したので、