教員 
2015年3月 9日 (月)
2015年2月20日 (金)
25年ぶりの再会
この日はお母さまもご一緒に来てくださり、
「発音の宿題もあり、厳しかったけれど、こうして話もでき、
名古屋に買い物に出かけたりと、
この大学で学んでいる学生も、
2015年2月12日 (木)
2015年2月 9日 (月)
2015年2月 4日 (水)
2015年1月29日 (木)
2015年1月22日 (木)
2015年1月19日 (月)
教員研修会受講(教員)
連絡網・MLの作成、
出席を取られます。
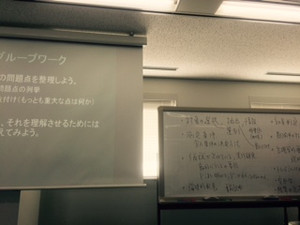 今週は、「教育評価」「研究法」「行動科学」「教育方法論」
今週は、「教育評価」「研究法」「行動科学」「教育方法論」
毎回グループワーク(GW)があり、チーム:「meだ!」
8人(PT5名、OT2名、ST1名)で時間制限の中、司会・
協力して遂行しています。
発表は、
今週は、学生気分を味わい、
課外での課題・
週末の宿題は、
来週は、日々の学習でのGWに加え、終盤のセミナー発表(
しかも、テーマは「
北は北海道、南は沖縄から参加の受講生の中には、
著名なベテランまで、
講師の先生との師弟関係のある方もおり、
まだ始まったばかりですが、沢山学び、
2014年12月 3日 (水)
実習事前訪問
大分東部病院は、
部長以下、
つられてウキウキして、あんなことこんなことできる!

大分赤十字病院は急性期で、「ICUからも呼ばれます。」
夕方からは、大分県士会のワーキンググループの会合があり、
両病院のスタッフも集まるとのことで、地域での連携もよく、
両病院とも楽しく充実した実習ができそうです。
2014年11月14日 (金)
学外活動(教員)
聖隷クリストファー大学は保健医療福祉の総合大学として
その特色
地域との連携・
教育・
「保健福祉実践開発研究センター」を立ち上げ、
"地域と歩む"
地域との共同事業・研究や専門職研修・
また地域に開かれた相談窓口となり、
更なる質の向上と課題解決のために積極的に
静岡県立浜名特別支援学校から保健福祉実践開発研究センターに
研
研修会のタイトルは「ST(言語)研修 子どものことばの発達と支援」、
特別支援学校の先生方は児童・

先生方がとても熱心に聞いてくださっているので、
これも話したいと気持ちが盛り上がり、
研修会の前後で一部の先生方とお話をする機会があり、
何
学校の先生と言語聴覚士、専門性の違う者同士が
児童・
学校現場の声を聞かせていただける貴重な機会でした。












