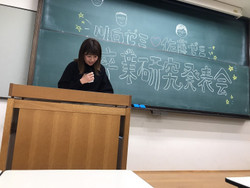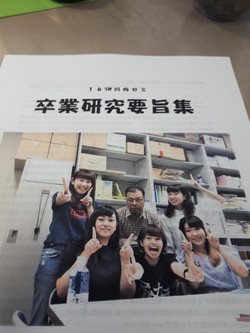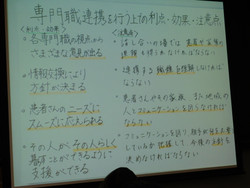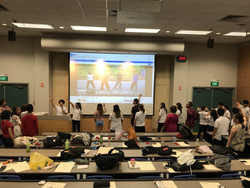シンガポールでの海外研修を終えた学生が8日、無事に帰国いたしました。
併せて最終レポートが届きましたので、抜粋して掲載いたします。
。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。.。・.。.。・.。*゚+。。.。・.。*゚+。。
今回の研修で、シンガポールでは日本より急速に高齢化が進んでいるが、「中央積立金」というものがあり、給料から17%が引かれて年々積み立てていくという制度がある、ということを知った。
これは障害を負ったときなどに使えるお金となる。
しかしサービスを受けるにしても、治療を受けるにしても無料ではないので、仕事をして稼がなければ将来困ることから、シンガポールでは「働く」ということを人々に強調していた。
また前回も伝えたとおり、シンガポールでは糖尿病が多く、2025年には糖尿病患者が100万人になると言われているほどである。
糖尿病を改善するために政府は1日に1万歩歩くように万歩計を無料で配っており、このやり方は成功していることを知ったが、その他にも、みんなで運動してから仕事に就くような取り組みがあったり、飲み物を頼むときに砂糖を少なめに注文できるようになっていたりした。
少しでも糖尿病にならないための工夫がなされていること、また早期発見により失明を防ぐことができるため、早めに検診を受けるよう勧められていることがわかった。
一方、研修中訪問したあるデイサービスは8人のスタッフのほか、200人ものボランティアで運営されていた。
ボランティアは31%が50歳以上であり、この方達は「長年働いた社会に恩返しをしたい」と思っている方や、「人々のために活動したい」と思っている方たちであり、こうした人が率先して施設運営に協力していることを理解した。
私が一番驚いたことは、シンガポールには精神病院が1つしかないことである。
大規模病院の中の精神科病棟はあるが、精神科だけの病院が1つというのは日本と大きく異なる点であると思った。
また患者さんが制度の利用を断ったような場合、制度を優先させるのか、患者の意見を尊重するのかという選択が迫られるが、日本と同様に患者さんの意思を尊重していることがわかった。
また、「障がいのある人に社会が仕事を与えないのは、周りの人たちがその人たちをどのように扱っていいのかわからないから」という説明を受けた。
これに関しては「わかるようになることを期待している」と聞いたので、具体的にどのようなことをしてわかってもらおうとしているのか、さらに興味を持つこともできた。
3月に今度はシンガポールナンヤン理工学院の人たちが来学する予定とのことなので、その時に質問したい。
またそれまでにもう少し視野を広げてさらに調べ学習していきたいと思う。
(2年生 A.I)