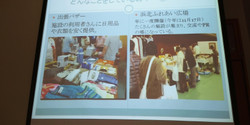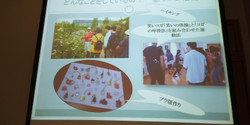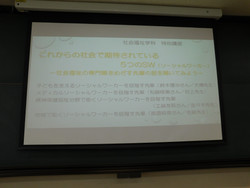日本多機能型精神科診療所研究会. 主催. 第5回. 多機能型精神科診療所研究会 浜松大会が、「地域の中での多機能のすすむべき道. ~現状からの発展を目指して~」の大会テーマのもと、2019年5月26日に浜松市内で行われました。
精神科病棟に日本の精神科医療が偏っていることはご存知の通りですが、医療構図が診療所にシフトし、かつ地域のメンタルヘルスの課題に対応していく仕組みとしての「多機能型精神科診療所」の研究が始まっています。
全国の「多機能型精神科診療所」を推進している、精神科医師や精神保健福祉士、作業療法士、看護師、公認心理師等約170人の参加者があり、大変盛り上がりました。
また、当日の運営には、本学卒業生(精神保健福祉士、作業療法士、看護師)も多数運営に携わっており、教員としても誇らしい気持ちになりました。
 (懇親会の様子)
(懇親会の様子)


(就労B型事業所製品の「ガチャガチャ」 我を忘れて2個、3個と・・・)
以下に、当日参加者として参加した今年3月に卒業した卒業生の感想を紹介します。
「懇親会と研修会では、県外の各地域の方々とお会いして話しを聞くことのできるまたとない貴重な機会でした。
研修会では、多機能型精神科診療所の現状や取り組んでいる活動について知りました。
そのなかで多機能型精神科診療所は、多職種連携での円滑な支援が出来るという強みを生かし、今後、精神科診療所や就労支援施設などの事業所がどのように効果的に多職種同士で連携していくべきかを考えていくことが必要ではないかと感じました。
そのために、事業所ひいては法人内で役割や理念など共通した目標を明確に持つことが重要だと学びました。」
 (大会では真剣な話し合いが・・・。)
(大会では真剣な話し合いが・・・。)
写真は「大会シンポジウム パラメディカルからみた地域での多機能型診療所の意義・展開」の様子です。
少子高齢化、地域社会のつながりの喪失、核家族化や家族関係の希薄化、児童虐待、ストレス社会、精神疾患の増加、ひきこもりの増加・長期化・高齢化等、日本社会は大きな課題を抱えています。
精神医療と福祉の間はもっと連携が必要であり、支援から予防へという発想も必要になります。
課題は多い領域ですが、このような機会を活かしながら、更に多機能型による実践が推進していくように関わりたいと思います。
浜松地区の活動を知りたい方は、2017年度に出版されました「「地域における多機能型精神科診療所実践マニュアルー乳幼児から成人までの地域包括ケアシステムを目指して」をご覧下さい。
⇒ http://kongoshuppan.co.jp/dm/1535.html
(社会福祉学科 教員)